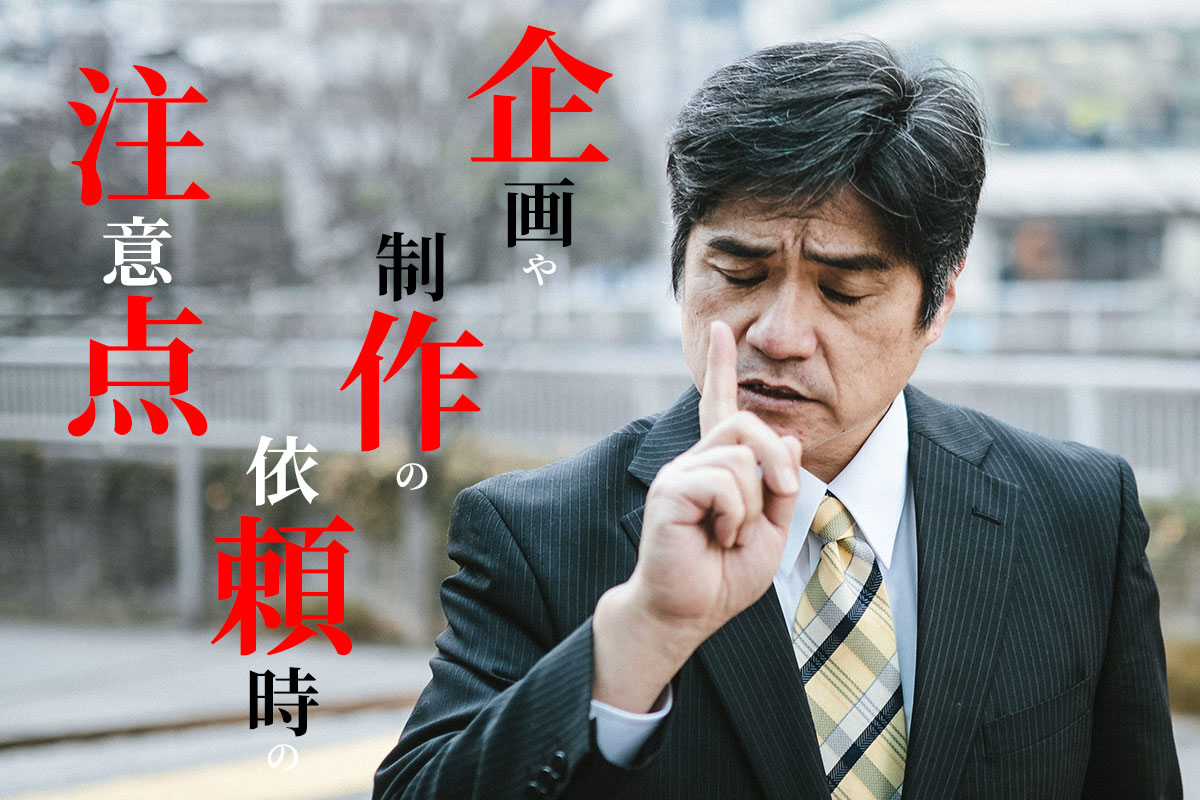まとめ方が難しいんですけど、まぁ、こんなこんな感じなのかな。また後日タイトル変えるかも。
内容としては制作を依頼したときにこんなトラブルがあった、こんな事象が起きたってとこで、「記録しておきたい記憶」シリーズほどではないし、「ディレクター突破ファイル」という内容でもないのですが、いくつかそれらに連なる注意事項を記述したいと思います。
制作会社の話もあれば、広告代理店等、WEBマーケティング会社の話もあります。僕の体験もあれば知人ディレクターから聞いた話もあります。
プロでないと判断つかないことがありますので、クライアント側の方々には判断つかないことが多いのですが、読んでおいて損はないかな、と。
まぁ、どこまでいっても、「餅は餅屋」なんだな、と思いますよ。
制作会社とSEO
すべてのWEB制作会社が「SEO」を分かっているわけではない。
主語がでかいので誤解してほしくないのですが、SEOをちゃんと施行してくれる制作会社さんもいます。ちゃんとSEOを理解して、意識してコーディングしてくれる方います。
でも、中には一切気にしないコーディングする方もいますし、指示を出さないとやってくれない方もいます。
制作会社に頼んだら勝手にSEOも完璧にやってくれると思ったら大間違いな話で、そもそもSEOをまったく分かってない制作会社もいたりします(その逆もまた然り)。
(担当するディレクター次第なとこでもありますが・・・)
コーダーさんってSEO知ってるんじゃないの?
僕の経験でいうと、ある制作会社に入社したときに、その会社が作ったWEBサイトを見ていたのですが、ディスクリプションが全ページ同じでした。
ディレクターとしての採用だったこともあり、そのサイトのコーディングを担当したコーダーさんに「なんでディスクリプションが全ページ同じなの?」と聞いたら「指示がなかったから」という回答でした。
「え、指示なくてもこのくらいのことはやるもんじゃないの?最低限のSEOを意識した制作をやるのが「制作」なんじゃないの?」 と思ったのですが、そうではない、と。他のコーダーさんに聞いても同じような反応でした。だって、検索エンジンにインデックスされなかったらリニューアルした意味や、作った意味なくない?と聞いたら、そもそもSEOは詳しくないし、コーディングとはまた別、という認識のようでした。sitemap.xmlやサーチコンソールへの登録なども指示がなければやらないし、やり方も知らないという回答でした。
SEOはマーケティング分野では?
WEB制作会社は制作のプロだし、コードの書き方(使用するタグ)も関わってくるので当然SEOを意識して作ってるものだと思ったのですが、実はまったく気にしてないし、「SEOはマーケティング分野」という認識に近いようで、ディレクターや営業部門が実施する作業では?という認識でした。これはショックでしたね。と同時に、ちゃんとした制作会社が作ったWEBサイトなのに、リニューアルの依頼時に調査すると、なんで「sitemap.xml」や「サーチコンソールへの登録がない」んだ、という事象があることに合点がいきました。制作会社って必ずしもSEOに強いわけじゃないのね、と(そもそもコンテンツSEOが当たり前なので、細かく気にしすぎても仕方ない、という考え方もありますが)。
よくよく考えてみると確かにコーダーさんの範疇ではないかも
言われて考えてみたらメタ文書に記述するタイトルやディスクリプション、ALTの内容、もう今では古いSEOですが、ページ内のキーワード濃度(もうこれ意味ないです)の調整など、こういったことはコーダーさんの仕事ではないですね。営業担当者がクライアント側の担当者と決める内容または、ディレクターが決める内容です。タイトルなんかは検索意識してつけたりもしますし、ディレクリプションもGoogleが自動で抽出することもありますが、それが100%いいわけでもないので。この会社もディレクターさんが次から次へと退職している会社でディレクターを育てる時間がないため、コーダーさんがディレクションをやった結果、このような事象が起きていました。
SEOは作業に自動的に含まれるわけじゃない
SEOと一言にまとめてしまうと誤解が生じますが(めっちゃ範囲広いしどこまでこだわるかにも依ります。ここで言うSEOですと内部SEOの範囲ですね)、狙ったワードで上位を狙うとかになってくると別メニューかもしれませんが。各社それぞれ方針はあるでしょうけど、「制作と1セットで最低限これくらいはやってくれるのでは?」という範囲としては、
・sitemap.xmlの生成と登録
・サーチコンソールへの登録(Bing WEBマスターツールズも)
・Googleを意識した各ページのタイトルとディスクリプション及びメタ文書をきっちりと作成(カノニカルタグ含む)
・ALTが必要な画像にはALTの入力(すべての画像でなくともいいと思っています)
・Googleビジネスプロフィールのオーナー登録または管理の推奨(これはSEOとは違うけど、最近は当たり前なので)
でしょうか。依頼時にどこまでやっていただけるか確認してみてください。
SNSマーケティングと一般常識
景品の告知に勝手に他社の製品写真は使っていい?
答えはアウトです。駄目です。OKしている会社もありますが、大体は事前に確認して、使用していい写真を担当者から提供受けるのが通常の流れです。
これは何かというと、企業などが行うプレゼントキャンペーンなどのキャンペーンの告知に使うバナーやチラシのデザインの話である。そこにプレゼントする家電品など何かしらの景品の画像をよく使うと思いますが、こういった画像は当然、許可取りをするのが通例で、許可取りするのが制作側の場合もあれば、クライアント側で許可取りして制作側に支給することもあります。
商品の写真は勝手にどんどん使って使っちゃっていいんですよ!
このときはSNSマーケティング会社の若い担当者だったか、営業だったか忘れましたが景品に使う商品の写真の許可取りは終了しているか?という質問に対して出てきた答えがびっくりである。
「こういったところ(=メーカー)は全部、『商品を売りたい』ばかりなので、商品の写真は勝手にどんどん使って使っちゃっていいんですよ!」 という信じられない発言が出てきた。全部?全部ってどこよ?確認したの?あと、そんなことあるわけないじゃん、と。勝手な思い込みであり解釈である。無責任なテキトー発言だ。
咄嗟にクチを挟んで反論した。こんなくだらないことをクライアントが鵜呑みにして損害を被ったらとんでもないことになるからである(そこまで責任持って発言していますか?マーケティング会社さん)。
許可取りは必要である
こういった景品に使う商品の写真に関しては許可がいるメーカーと許可が要らないメーカーがあるけど、明確に許可が要らないと記載されていない限りは許可を取ったほうがいい。
例えば、パナソニックなどは許可をしてくれている。
景品用の商品画像について
https://panasonic.jp/info/product_image.html
ダイソンなどは明確に勝手に利用することを禁じている
利用規約
https://www.jamesdysonaward.org/ja-jp/website-terms-of-use/
お掃除ロボット「ルンバ」で有名なiRobotでは専用の窓口を用意している。専用の窓口がある、ということは許可がいる、ということである
取材、販促利用について
https://www.irobot-jp.com/press/contact/
最近よく見かけるAmazonのギフトカードなどは条件が細かく記載されており、注釈を入れないといけなかったりもする。
法人向けAmazonギフトカード
https://www.amazon.co.jp/b?ie=UTF8&node=4731316051
つまり、各企業それぞれであり、それぞれに確認しなければいけないのである。
というか確認は当たり前であり、何も確認せずに憶測で「勝手に使っていいんですよ」などとクライアントに無責任に発言するのは絶対にあってはならないことである。
なぜ、こういったことを知っているかというと、以前、家電品や電気工具を卸す会社に勤めていたことがあり、展示会などを取りまとめる係+展示会のパンフを作っていたので許可取りが必要な会社もあることは知っていた(直接でなくても販売代理店がメーカーに許可取りをしているパターンもある)。
マーケティングは専門かもしれないが・・・
とこのように、マーケティングなどは専門で詳しいかもしれないが、それ以外のことはそうでもないこともある(普通は教育するんだけどね)。SNSという比較的新しい媒体のマーケティングであり、学生からそのままそういった新しいIT系のベンチャーに進んだことで、そういったことを学ぶ機会がなかったのかもしれない(だとしても一般常識で『他社製品を勝手に利用する』ということにおいて確認が必要かも、とは思わないのも不思議ではあるが)。また、ご多分にもれず、よくあることなんだけど、CMYKとRGBの違いがわからず、CMYKでバナーを作ってしまい、商品の色が違うということもあった。「制作」という作業に関わる以上、解像度とCMYKとRGBの違いくらいは理解しておいてほしいと思っています。
ちょっと小耳に挟んだ小話
とある有名SNSマーケティング会社の後始末
僕の知人が社長やっている制作会社のお話です。異業種からのSNSマーケティング会社に転換したみたいで結構有名な会社があるのですが、地元が近いためか、そのマーケ会社に頼んでどうにもならなくなった案件や作ったはいいけどその後にトラブルがあった案件などが流れてくるらしく、「その会社のアフターフォローが駄目でこっちに流れてくることがある」と言ってました。制作の基礎を知らないので、後先考えないんでしょうね・・・。
依頼時には作ったあとのこと「運用」も決めておいたほうがいいです。一時期、コーポレートサイトでブログを作る企業が多かったのですが、「運用」を考えていないことが多く、作って放置のパターンも結構ありました。これはブログ投稿の仕組みの導入が目的になってしまっており、「運用」が見えていなかった結果です。
わからないままに話を進めて、足りない準備
広告代理店さんやそれに近い動きをする大手の印刷会社さんなどにたまにいるのですが、WEB制作がわからないんだけど下請けさんやパートナー会社を同席させないため、クライアント側の要望をちゃんと理解できないままに話を持ってきたり、スコープ(その要望に対してどういった作業やデータや調査など様々な準備や対応といったとこでしょうか)が足らず、納品のときに、「そういやこれってどうなってるの?」で「え、なんですかそれ」ってこともあったりします。制作側からも「事前に言ってもらわないと困る!」ということが多いので、この担当さん大丈夫かな?と思った場合は制作会社さんや、その会社のディレクターさんにも同席いただいたほうがいいでしょう(割とこの手のトラブル多くて、制作会社や開発会社がなんとかするしかないってパターン多かったりする)。
とまぁ自分の経験を交えて記述したわけですけど、もちろんちゃんとしたマーケティング会社、企画会社、制作会社います。むしろそちらのほうが多いくらいでしょう。制作は制作会社じゃなきゃ駄目ってわけでもなく、マーケティング会社でもしっかりとした制作会社と手を組んでいる会社もいます。依頼を出される際は、どういった方が制作を実行されるのか、その方や、その企業の実績、その後の運用体制、支援体制などもしっかりと確認されたうえで依頼を検討ください。(特に、WEBマーケティングや企画が得意だと言う割に企業WEBサイトのメールフォームに営業メールを送りつけてくるWEBマーケティング会社は信用出来ません。自分で「WEBを使ったマーケティング出来ていません」って言ってるようなもんですよ、あれ。)