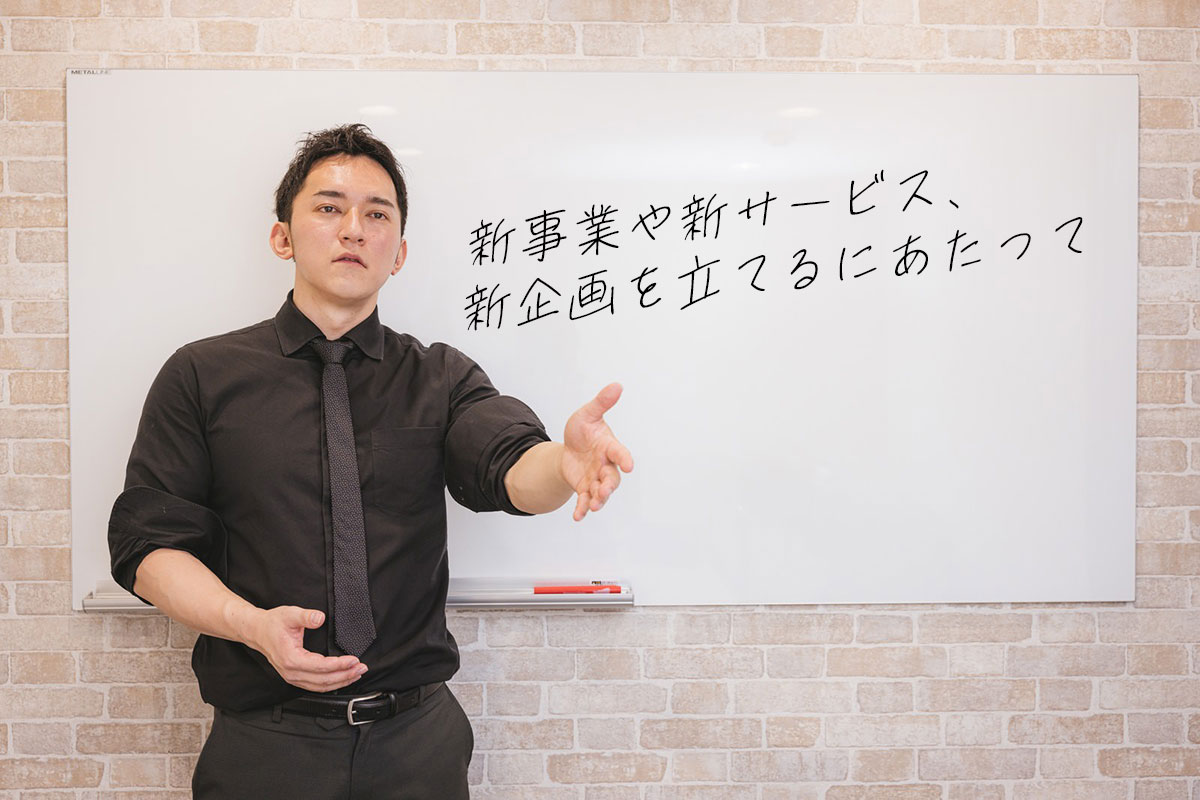先日、Xにて「制作会社が自社サービス(=制作案件じゃなくて、自社が提供するサービスでそれ単体で売上が立つもの)を起ち上げると、大体うまく行かないことが多い。それはマーケティングの発想がないから」といった趣旨の投稿をされている方がみえまして、本当にその通りだと思いました。別に制作会社に限ったことではないですが、制作会社に在籍していた際にそういった経験を何度かしていることもあって、骨身に沁みています。
いくらでも事例事象は書けるのですが、僕も20代の頃はよくサービスを考えたり、自社事業企画を考えていたのですが、
・マネタイズが弱い(やったら面白そうだけど、じゃ、それが収益になるのか?というと・・・)
・希望的観測が強い(冷静に市場やターゲットが見えていない)→要するにマーケティング脳がない
・「なぜそうなのか」で始まるのではなく、「こうします」だから理由付けが弱い
といった指摘を言われて、それまでは「アイデアマン」的な自負があったんですけど、単に「思いつき」なだけであることを自覚しました。
自分の企画やアイデアって「やってみたい」から冷静に見えてなかったり、自身に都合よく考えてしまうんですよね。俯瞰とか客観で見えていない、というか。
本人はマーケティング脳あるつもりでも第三者からすると、都合の良い発想や解釈でしかなかったり。忖度があったり。これはSWOT分析の強みの認識とも似ていますが。
では、実際の事例をもとに話を進めたいと思います。
Contents
制作会社全般抱えている悩み
僕もそうですけど、制作会社って「お客様の販促宣伝物やなにか」を作って収益を上げているため、他社依存というか。どうしてもそうなってしまいます。売る「商品」がないため、売るものは「技術」や「経験」「知識」といったものを売って、それが「制作物」に形を変えてお金になります。
営業しても案件がないときはないですし、新規獲得も中々難しいです。通常は付き合いのある会社に依頼しますからね。大手の制作会社さんであれば専任の営業さんもいるでしょうし、その人数も多いし、付き合っている広告代理店さんも多いので、なにか案件は出てくるでしょう。しかし、中小の制作会社になると営業は社長だけとかディレクターが営業も兼ねていたり、と中々「営業に集中」は難しいです。
そこで考えるわけです。社員を守るためにも、「仕事がない(=お金がない)」なら、「自分たちで仕事(=お金)を生み出せばいい、と。自分たちでなにか新サービスや新事業を立ち上げよう、そう考えるのは至極当然のことかと思います。先程申し上げたように、売れるのは「技術」や「知識」ですので、例えば「知識を売る=WEBスクールやセミナー」だったり、「技術を売る=作品を素材として販売」だったり。そうすることでお客さんに頼らない(=制作だけじゃない)「売上」を作ろうとします。そうして、いろんな自社サービスや自社企画が起ち上がります。
今までに起ち上げた企画やサービスとその結果
お客さんの商品を制作会社が売るECショップ
制作案件をいただくと同時に、「そのお客さんの会社の商品を自分たちで売ろう」という発想で起ち上げたネットショップです。人生で初めて起ち上げたショップで、カート付きレンタルサーバーを借りて始めました。通販会社さんも何社かお客さんにみえたので、商品を集めやすく、お客さんの商品を自分たちで売るわけですからお客さんも喜ぶし、自分たちの利益にもつながる!と信じてスタートしました。
実際にやってみた感じたのは、ネットショップってそんなに簡単に商品売れないし、在庫抱える余裕ないから、「受注したら発注」で商品が実際に売れたらお客さんの会社に商品を取りに行く(送料や納期の関係で送ってもらうのは無理だった)という仕組みだったり、在庫を抱えないということは、仕入れ値が高いので利益幅も薄いんですよ。それにお客さん自身もショップで同じ商品を売ってますからね。相手は楽天などのショッピングモール内のショップですが、こちらは独立店舗。ユーザーの流入量も商品数も違います。商品が置いてあるだけでは駄目でして、盛り上げるための演出や情報発信とかしなければいけないのに、そのやり方もわからず、制作業の片手間になってしまい、上手くいきませんでした。発想は良かったと思うんですけど、「お店の経営」という認識が足りなかったように思います。
お客さんを招いてデザインセミナー
これは聞いた話ですが。とある印刷会社が「自身でチラシを作れるデザインセミナー」というセミナーを無料で開催し、自社のお客さんを招きました。営業部が企画し、デザイン部が講師となってチラシの作成方法を無償で教える内容のようですが、タダで自分たちの技術を売ってしまってどうするんでしょうか?そもそも「無料でデザインを学ぶ」「自分でチラシをつくる」という発想の時点で、そのセミナーに参加された方々はその印刷会社の顧客になりえない方々のような気がします。
もしかしたら、デザインセミナーによって自身がデザインを覚えたことで印刷の依頼が増える(デザイン代が高い、もったいないからチラシの依頼がない)と思ったのでしょうか。もし、そうだとするなら、自身の商材を間違えていますね。彼らはデザインの腕や技術、知識、経験で制作される「制作物」を売るのではなく、「紙」を売っていたことになります。
TCD社のマネしてデザインテンプレート販売
TCDという会社さんがあります。制作業界の方であれば誰もがご存知の「WordPress」のテーマを販売している会社さんです。単純にTCDさんの真似をしようと社長が立案しました。何をどうするかというと、制作会社だったため、様々な企業さんの案件でいろんなWEBデザインのデータが作成されます。中には選ばれなかったボツ案もあるわけですが、「そのボツ案をテーマファイル化して売ろう」という企画でした。確かにオリジナルで起こしたデザインをそのまま放置しててしまうのはもったいないので、こういう再利用するような事業をやったらいいんじゃないか、と思う気持ちはわかります。
TCDさんよりも安くテーマを配布して、WEb広告やSNSで拡散したらきっと売れるし、テーマファイルは定期的に追加していけば年間で何百万)という利益(確か1年後には800万の利益だったかな・・・になる、というシミュレーションで役員たちは拍手喝采でした。
ただ、制作の現場にいる我々からすると、
・売れるレベルのテーマファイルが1種類しかないのに事業スタートって流石に無理じゃない?
・TCDや有償配布されている海外のテーマとかのレベルを超えているとは思えない
・3000円~5000円くらいなら売れるかもしれないが、30000円~50000円は流石に無理だと思う
・通常の制作案件の納期に追われている中で定期的にデザインとコーディング作業が出来るのか?
・再販や再配布の対策は?
・WPやPHPのバージョンアップ時にそのテーマファイルもバージョンアップさせるのか?
・WEB広告やSNS経由でユーザーが入ってきてもCV率は1%あれば上等という世界で、そんなに売れる?
と疑問や懸念事項を伝えたところ社長は「何を言っているのかわからない」とシャットダウンされました。言い返せなかったんだろうなと思います。
テーマファイルの脆弱性対策やバージョンアップ時の対応なんて、「対応しない」でしたからね。お金払って買ったテーマファイルのアップデート一切しない(要は次のテーマファイルを買えってことかと。それでいて毎年の利用料払えっていう内容)ではお客さんさすがに怒るんじゃないかと。
結局、この事業はスタートしなかったんですけど、権力を持っている人間が「ただ単にそれをやりたいだけ」で計画性もシミュレーションも都合のいい数字を並べて、「こうなるといいなぁシミュレーション」というシミュレーションを使って「効率のいい生産性の高い事業」と見せていただけでした。怖いのは営業部長が「社長のシミュレーションの数字がおかしくても、社長がやりたいと言ってるんだから、やらせてあげるべきだ。それが会社員なんだから。」と後で怒られました・・・。でもね、そんなユーザーを騙すような、お客さんからクレームが出るような事業はしないほうがいいですって。
フリーペーパー
これは実際に創刊したんですけど、半年くらいで終了したかな。これも「権力を持っている人間が「ただ単にそれをやりたいだけ」」という企画で最初から計画に無理を感じていたのですが、結局スタートしました。
元々はとあるフリーペーパーが廃刊するから、そこに出稿されているお客さんを譲り受けて展開させる、という話で、要は「地場とお客さんを引き継ぐので最初から売上が見込める事業」という話でした。この話を聞いて、社長のさらに上にいるオーナー経営者的な方に意見をしました。
・本当にそんな上手い話になっているのか?(何度もそういう経験をしてきているが)相手の話を社長がまた自分に都合のいいように解釈+盛っているんじゃないのか?
・フリーペーパー激戦区である地域で、ノウハウもない、定期読者もいない新雑誌が生き残るのはかなり厳しい
・世の中はペーパーレスに向かっていて、フリーペーパーが減っている世の中でフリーペーパーに手を出す意味がわからない
・WEB媒体でフリーペーパー的なキュレーションサイトを起ち上げて記事出稿しませんか?なら、記事も残るしSEO的にもいいし理解できるけど紙媒体は無理
・お客さんの獲得に動く営業マンが社員では僕だけで、あとは外部のライターさんと、営業経験どころか、普通の社会人経験すらない半グレ
・しかも全員片手間にしか営業できない
・一度は出してくれるお店もあると思いますけど、効果がなければ翌月は多分出さないです。飲食店、美容院の店長さんやオーナーさん、B2Cで小売で生計を立てている方々はかなりシビアですけど大丈夫ですか?
(せっかくお客さんを掴んできても、雑誌の拡散や配布場所が悪ければ効果が薄いとみなされ、翌月は出稿いただけない)
という話をしたのですが、「大丈夫」としか言わない。「反対意見は言いましたからね。会社員なんで「やれ」と言われたら全力で取り組みますが。かなり難しいということはご理解ください」と伝え取り組みました。
創刊号は皆さんお祝いも兼ねていたり、ユーザーにも手にとってもらえることが多いということで黒字になりましたが、創刊号に広告出稿したお店からは「広告費用に見合った来店がない」といった理由等で次月の出稿を断られました。20代のとき、印刷物のデザイナーをやっていた際に飛び込み営業でいろんなお店に営業仕掛けてるんでわかってたんですよね。お付き合いで毎月何万も出してくれるお店なんてそうそういないってことは。店舗経営をされている方ってかなり厳しいことを言われます。まして紙媒体でしょ?しかも他にもいっぱい競合のフリーペーパーがあるなかで。見通しが甘いんですよね。
上手くいかない原因はなにか?
上記で挙げたのは「制作会社で起ち上げた事業」ですけど、先述したように別に「制作会社」だけがこのように上手くいかないわけではないです。どの業種、どの業界、どの企業でも起こり得ることです。
上記の事例で言うと、
・実際の店舗運営のイメージや売り出してからのシミュレーションや想像が足りていない
・実際にスタートしてからのリスクヘッジを考えていない(楽観視や想像力が足りてない)
・自社の商品や自社の環境、状況を冷静に客観視出来ていない(きっとお客さんは申し込んでくるだろう、という希望的観測)
・事業性を考えずにタダ単に「やってみたいだけ」
・自身のプライドを満足させるために起こした事業
・ユーザーの動きや数字が自身に都合のいい設定になっている(スコープや調査が希望的観測になっている)
・収益ポイントが謎または収益性が低すぎる(採算が合ってない)
といったところでしょうか。
もちろん、上記の理由に当てはまっていても成功させてしまう、軌道に乗せてしまう剛腕・辣腕な方もいると思いますが、そのためには潤沢な資金力や人脈、その企業の持つブランド力(=歴史や世の中の信頼性)が必要だったりします。でも、そういったものを持っている企業って思いつきで動きませんし、もっと慎重に動くかと思います。大体、会社の収益を上げるために始めた新しい事業(=手段)を軌道に乗せるべく、大量に資金投下するって本末転倒な気もしますし(これが税金対策の意味も含め新事業にチャレンジで投資ならわかりますけどね)。
これ、なんで上手くいかないかって、結局「需要と供給が成り立ってない」からなんですよね。無理やり需要を作り出して供給をするならまだしも、需要がない場所へ供給を売り込んでいる感じでしょうか。
事業の起ち上げって
「マーケティング脳」ってそもそもなんだろうな?とも思いますが、「収益性のある仕組み(=事業)を考えられる脳」なのかな、と。もっといい表現があるかもしれませんが、端的に表すとこんな感じでしょうか。
そして、収益性があるかどうかの判断要素って幾つかあるとは思いますが、その1つに数えられるものとして、「その事業は何らかの問題を解決する事業なのか?」というものがあります。
いわゆる「ソリューション」的な発想ですが、事業の大きさやチャンスは「その問題」が大きい(言い換えれば、社会的な問題、公共的な問題)ほど事業性やビジネスチャンスは大きくなる傾向があります。
例えば
・ごみ問題が社会問題になりつつある → リサイクル事業 が発達
・水が汚れて飲めなくなる時代が来る? → 「水」を買う時代が到来
・共働きや核家族化で連絡手段の多様化? → 携帯電話事業の発展(無理やりすぎますかね?)
といった具合に、「何かしらの問題があって、それを解決する」そこに事業性があるわけです。
個人的な経験からですと(事業って言うレベルではないですが)、
・タイにある日本の家電メーカーの工場が大雨で床上浸水で生産ライン停止 → 国内の在庫が減るから需要が高まるチャンス → ECに在庫商品(型落ち)を一気に掲載 → 売れ残っていた在庫品一掃
・(太陽光パネルブーム時に)太陽光発電パネルの架台の設置に時間がかかる+費用もかかる → 架台の下に置くコンクリートブロックを商品開発して大幅に時間と費用をカット → 全国から問い合わせ
といった具合に。上手くハマるとこんなにスムーズにいくのか、と思ったことがあります。両方とも社会問題というよりは「自社の顧客の多くが持つ問題点の解決」ではありますが。
では、上記の「上手くいかなかった事例」は何の問題を解決する内容だったのか、というと「何も解決していません」。
敢えて言うなら、「自社の売上を補填するため」であり「自社の売上が安定していない問題」を解決する事業です。辛いのはわかるんですけど、社会的な問題でもないし、公共的な問題でもないです。
だから上手くいってないんですよね。
まとめ
そうなると新事業や新企画をうまく進めていくためには
①事業性(例えば何らかの社会問題や顧客の持つ問題点の解決策)✕②収益性(問題解決策をどのように収益に返還させるか)✕③告知拡散力(市場へ認知させるための営業力や広告力は必要)
という方程式が成り立つのかな。経済学者でもマーケターでもなく自分の経験上からの回答ではありますが。
①がなければ「自社が儲かるためのサービス」で需要は低い、②がないとボランティア状態だったり薄利多売ですね。③がないと誰にも知られない、ということになる。
そして、この①の社会問題が一過性のものだった場合、それは単にブーム・流行になるので早々に廃れていきます。上記でいうと家電製品も太陽光の架台ブロックもかなり売れましたが、一過性が強いため、その「問題」はすぐ解消されて事業性は薄くなっていき、長く取り組める事業ではない、ことになります。
もしかしたら上記の事例も同じサービスや事業だったとしても中身の目的や見せ方、運用を変えることで結果は変わったかもしれないですね。
僕も同じく制作系の人間なので自分でなにかサービスをとは思いますが、「こんなWEBサービスはどうだろうか?」やはり僕一人では難しいな、と感じています。①と②はクリアしている・・・と思い込んではいるんですけどね。自分が立てた企画を客観視するのって難しいです。
お客さんや社会の問題を解決することで自社の問題も解決出来る、この発想が大事なのかもしれません。