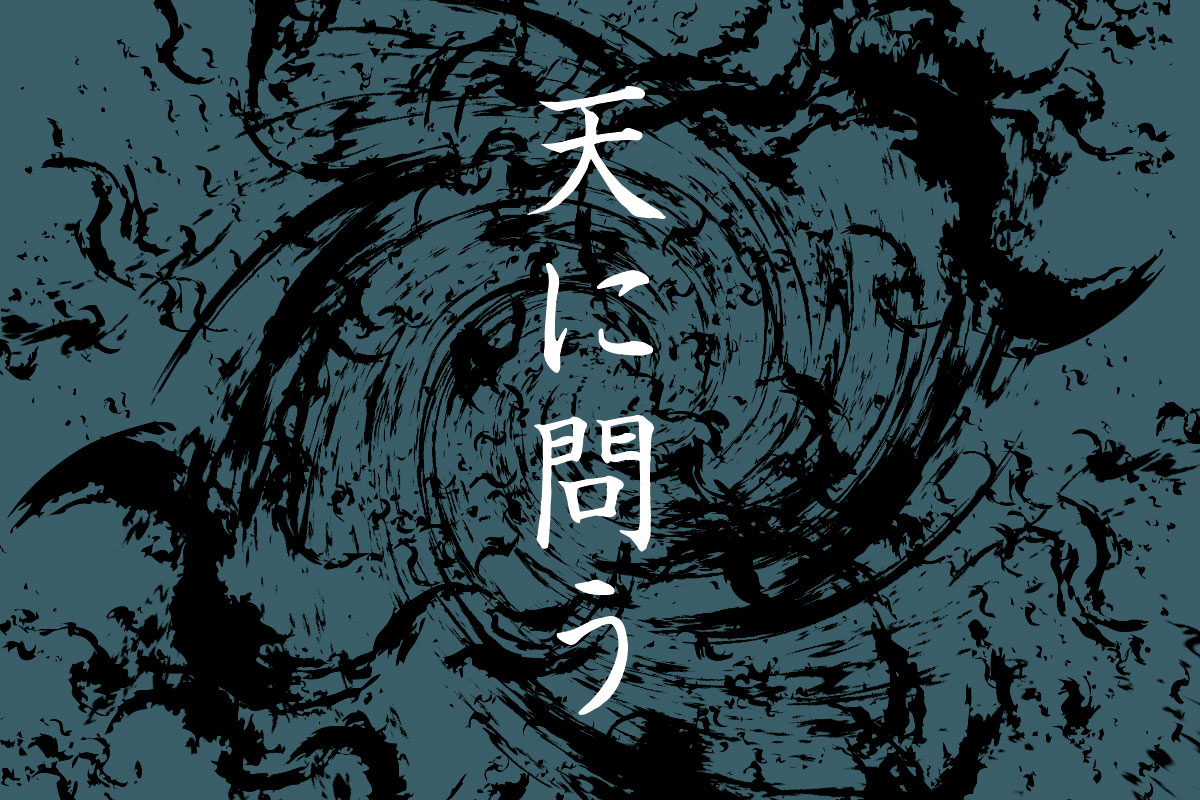第二章 「去る者」
柏の死
その冬、柏が逝った。
起は十六になっていた。
雪の降る午後、いつものように書庫の窓から庭を見やったが、そこに柏の姿はなかった。
静かな情景だった。
鳥の影も、子どもの声もない。
ただ庭先の老いた柿の木に積もった雪が、音を立てて落ちた。
それが柏の気配の名残のように思えた。
眼の前に広がる庭は、雪に覆われ、ただ白く静まっていた。
起は目を閉じた。
まぶたの裏に浮かぶのは、柏との日々ばかりだった。
幼い頃から側にいた柏は、従者の枠を超えた存在だった。兄とも、父とも異なる、起にとって唯一無二の存在だった。
ともに歩いたあの道。
商鞅が生まれ育ったと伝わる村落があると聞けば、柏とともにその地を訪ねた。
ひっそりとした村の一隅で、寡黙な老村人がわずかに口を開いたが、語られるのは風の噂のような曖昧な話ばかりで、誰ひとり、若き日の商鞅をその眼で見た者はいなかった。
時の流れが記憶を呑み込み、志ある者の名までもが、風の中に消えていく——名も志も、やがて塵のように散っていくことを、起は知ったのだった。
また、近隣に旅の商人や、遊説を旨とする学者が現れたと聞けば、柏の手引きで足を運んだこともある。
中でも、ひときわ印象に残った学者がいた。
名を慎到(しんとう)と名乗り、斉へ向かう途上だと語っていた。
その言葉は冗長を排し、理にかなうことのみを貫こうとする硬質な響きを帯びていた。
幼い起の胸にも、それは明確な印象を残した——
「任賢使能、法理立世(実力をもって事をなすべし、理を以て世を治むべし)」
慎到の語る理念には、どこか商鞅と通ずるものを感じたのだった。
ふと目を開けると、雪はなお降り続けていた。
白く塗りこめられた庭に、一対の足跡もない。
柏が、もうこの世にいないという事実が、ようやく現実として胸に沈んできた。
父・粛
柏がこの世を去ったあとも、起は街へ出た。
耳を澄ませ、目を凝らし、商鞅にまつわる僅かな伝聞すら拾い上げようとした。それはもはや執念に近いものであった。
それを、父・公孫粛は苦々しく見ていた。
粛には息子が二人いる。
長子・成は正室の子であり、次子・起は側室の子であった。
起の母は、もうこの世にはいない。それでも粛は父として、両者に差を設けぬよう心を砕いてきた。
学問においても、言葉においても、愛情においても。
しかし結果は、あまりに異なっていた。
成はすでに仕官している。
地位は高くないが、謹直にして非をせず、若き士として名を得ている。
親から見ても誇らしい息子であり、公孫家を支える柱たる器量をそなえていた。
対して、起は外にばかり目を向けていた。
柏と共に歩き、商鞅に心を寄せ、今なお父祖の教えに背を向けるような振る舞いを続けている。
粛の胸には、ふとある疑念が浮かぶ。
──母親の血の差なのかもしれぬ、と。
この国において、血脈と身分の重さは、もはや理と化している。人の器は生まれに宿る。卑しき出自の者は、どこかで分を誤るものだ。
「柏のような者を近づけすぎたか……」
起が柏と歩いた日々は、まるで柏の子のようだった。
あの男に情を移したのが、過ちであったかもしれぬ。
しかも、あの「商鞅狂い」である。
起は知らぬ。商鞅がこの衛の国にいかなる影を落としたかを。衛人が、いかに肩身を狭くしているかを──。
粛の嘆きは、理に始まり、情で終わる。
兄・成
兄・成にも、また胸のうちがあった。
幼い頃、弟の奔放さをうらやましく思ったこともある。だが、それを表に出すことはなかった。
正室の子として、家を背負う自覚が早くから彼を律した。
柏と共に市井を歩く弟の姿に、成の母は眉をひそめた。
「使用人と遊ぶなど、公孫の名を貶める」と。
成もまた、それが正しいと信じた。父母を喜ばせる、それが孝であり、忠であると。だからこそ、弟にもそれを求めた。
しかし、起は応じぬ。年を経てもなお、空理空論に傾き、商鞅の影を追う。現実を見ようとしない。
「此奴は、何かが根本的に違う」
そう思ったとき、成の中で何かが静かに切れた。弟を叱る父に対しても、起は怯むことすらしない。かえって煙たがるような仕草を見せる。
──この弟を、いずれ自分が養うことになるのか。
商鞅を語る弟は、しかしその本質を知らぬ。ただの影法師を、神のように崇めているにすぎぬ。
成の胸にあるのは、誇りであり、責任であり、そして言葉にしえぬ哀しみであった。
それぞれの思惑
そのような父と兄とともに過ごす日々は、起にとっては、窮屈であり、また退屈でもあった。
思えば、そうした息の詰まる家を離れ、外気を吸う機会を与えてくれた柏は、もはやいない。
「……国外に、留学できぬものか……」
独語する声は、吐く息とともに白く凍り、書庫の片隅に消えた。
学問とあれば、父も学資や滞在費の工面を考えてくれるかもしれぬ。それは、父の美徳でもあった。
だが、起の本心は学を志すよりも、ただこの家、この国にいることの耐えがたさにあった。
(今、諸国で勢いのある国といえば――秦、趙、斉か。魏もなお強国に数えられるが、魏は……)
魏は、起にとっては、商鞅の志を拒んだ国である。その誤謬を知る者は、もはや少ないであろう。
秦はどうか……秦はさすがに遠い。そして国情が全くわからない。全くの伝手のない自分が行くには障壁が多いように感じる。柏の知人や友人が秦にいたり……そんな都合よくはいかないか……。
そうなると、趙か斉ということになるが――。
「そういえば、慎到殿が斉へ赴くと申しておったな」
頼りない縁であっても、ないよりはよほどよい。たしか彼は「稷下の学士」として招かれたのだと語っていた。
斉の威王や宣王は、学者を厚遇し、稷門のあたりに彼らのための館を設け、多額の資を供出していたという。
そうした中で、諸子百家の議論が闘わされる。自由闊達な空気が流れ、才ある者が己の志を試すにふさわしい。
(斉こそ、行くべき地かもしれぬ……)
その数日後、起は意を決し、父の部屋に趣き、読書中の父に願い出た。
「父上、私に斉への留学をお許しくださいませ。あちらで学を深め、ゆくゆくはこの国のため、世のためになすべきことをなしたいと考えております」
もちろん、「この家にいたくない」という本音は、微塵も出さぬよう言葉を選んだ。演技というほどではないが、声色に真摯さを含ませ、熱のこもった瞳をもって訴えた。
父は黙してしばらく、やがて短く、「考えておく」とだけ言い残した。
意外であった。起は、即座に却下されるものと覚悟していたが父の思わぬ反応に小躍りしたくなる気分だった。
(この家を出て、好きなことを学べるかもしれぬ)
それゆえ、書斎の外ににもう一人の人影があったことに、気づかなかった。
その人影は、兄・成であった。その夜、成は父に詰め寄った。
「父上、あの者に斉への遊学など、到底許すべきではありませぬ。我が家は裕福ではなく、しかもあの者は、ただ家から逃れたいという一心で言っているだけにすぎませぬ。
亡き者の影を追い、現実から逃避しているような者に、未来を託すなど、笑止千万」
父・粛もまた、内心ではそうした懸念を抱いていたが、それでも起の言葉に、ごくわずかな、かすかな可能性を見ていた。しかし、成の一言が、その芽を摘むに足る理を持っていた。
「それに、国外へ出ることで、余計な疑念を招くことにもなりましょう」
成がそう言い添えると、粛は「……起には、少しだけだが、違う可能性があるようにも見えた。だが……わかった。お前の言うとおりだ」と頷いた。
違(たが)える父子
その数日後、起は父に呼ばれた。
その声に、察しはついていた。返事を得る日が来たのだと。
だが、父の部屋に入ると、起の目は硬く見開かれた。父の隣に、兄・成が座していたのだ。
「さて、起よ。斉への留学の件、認められぬ」
短く、抑えた声で言い渡された。
「父上、なぜですか?私は本当に学問がしたいのです。どうか、斉へ行かせてくださいませ。自らの力を、天に問うてみたいのです」
声は懇願に変わった。この機を逸すれば、一生、衛の地を出られぬ。そんな予感がした。
「白々しい」
声の主は兄・成であった。乾ききった声が、冷や水のように響く。
「学問などと申して、貴様はこの家から逃れたいだけであろう。商鞅、商鞅と――。貴様は、あの男が何をしたのか、知っているのか。秦の犬となり、魏を欺き、公子卬を謀って虜にした、卑怯者よ」
起の胸が煮えた。尊敬する人物を、面と向かって貶されて、黙していられようか。
「たしかに、策をもって敵将を陥れたのは事実かもしれません。しかし、それこそが智将のなせる業。無用な犠牲を防ぎ、兵を守る手だてではありませんか。彼の志を、どうか見誤らぬでくださいませ」
押し殺してきた想いが、堰を切って流れ出す。
「なぜ、父上も兄上も、商鞅の名を誇りに思わぬのですか?衛の出でありながら、魏の宰相に認められ、秦の変革をなし遂げた。彼ほど、衛の才の高さを天下に示した者がおりましょうか」
その言葉に、粛の目が、わずかに動いた。
「……起よ。衛とは、秦のような辺境の蛮国ではない。周の康叔が封ぜられてより、礼と智とをもって国を治めてきた。文の力こそ、我が国の道であり、誇りでもある。孔子が三たび訪れた国――それが衛よ」
そして声の調子を沈めて、父は続けた。
「そなたが尊ぶ商鞅の最期はいかなるものであったか。法で縛った結果、法に殺された。新たに即位した秦王に嫌われ、兵を差し向けられた。自領で反乱を起こし、乱戦のなかで討ち死にだ。その亡骸も車裂の刑にあい、晒された。――父として、そなたにそのような末路を歩ませることは、断じてできぬ」
父・粛の声には怒気はなく、むしろ静謐な慈愛が滲んでいた。それがかえって起の胸を締めつけた。
「それに、柏が商鞅の邸で働いていたことは知っているな?柏の足が不自由だったのを覚えておろう……。あやつは、商鞅の反乱に加担したらしい。ところが秦軍との戦のなかで負傷し、捕らえられた。奴隷として売られていたのを、儂が不憫に思い、雇ったのだ。――ひとりの、分不相応な夢が、周囲の者の人生をも狂わせるのだ」
そうだったのか……。
柏は、商鞅とともに起ちあがり、戦ったのであろう。衰亡を潔しとせず、沈黙を拒み、生をもって抗し、天に己が身の価値を問うたのである。――足を失い、名を失い、ついには沈黙のうちにその過去を封じた老僕。
かつて柏に、商鞅は今も生きているのかと問うたときのことを、起は思い出していた。
柏はその問いに、はっきりと否を告げることなく、静かに目を伏せ、ただ「もう、随分と前に亡くなられております」とだけ応えた。
それは曖昧な返答でありながら、どこか含みと翳りを帯びた声音であった。
あのとき柏は、何かを隠していたのだ──今なら、それがわかる。
柏は、商鞅の最期を、遠くから見届けたのではない。ともに戦い、命を賭けたのだ。
沈黙は、語らぬためではなく、語れぬ過去を背負っていたからこそのものであった。
かつて反乱に加担していた、とわかれば今の雇い主である公孫粛や起にも何かしらの迷惑がかかるかもしれない。
柏は、そう考えていたのかもしれぬ。誰にも知られぬ忠義が、不自由な足の影にひそみ、長き沈黙のなかに封じられていたのだ。
その歩みの遅さは、老いだけによるものではなかったのだ。
起は、はじめて柏の沈黙の深さと重さを知った。
そして、その背に、自らもまた背負わねばならぬ何かを見出した。
起は、ただ黙し、父の言葉に深く耳を傾けていた。
老いの兆しを見せぬ厳格な容貌。その目に宿る火は、かつて若き日の志を守るため、幾度も身を挺して家門を支えた男のものであった。
しかし、いまはただ、城の石垣のように冷たく、起の胸を締めつけた。
「おまえは“起(たつ)”にはなれぬ。世に問う器ではない」
言葉は剣であった。誤魔化しも慰めもない。
父の厳しき眼差しと、その傍らに浮かぶ兄の冷笑。
ただ事実として告げられたその言葉に、怒りが湧くよりも早く、起のうちには深く冷たい虚無が立ち上っていた。
それは、無明の闇に似ていた。
兄・成は、横に坐してなお、勝ち誇った色を隠そうとせず、口の端にかすかな笑みを浮かべていた。父・粛は、ただ黙していた。
(家を尺度に、国を尺度に、世を測る者たちよ――)
起はそう叫びたくなる衝動を辛うじて抑えた。口にすれば、ますます隔てが深まるだけと、冷ややかに悟ったのである。
出立の朝
夜、起は鬱々たる思いを抱えて床に就き、明朝にはこの家を発つことを決めた。
留学を願い出て拒まれたことも、兄に蔑まれたことも、天が与えた一つのきっかけにすぎぬ。そう思うことにした。
幸い季節は春である。凍えることもないだろう。
起は粗末ながらも旅支度を整え、夜明けを待った。
朝、家人を起こさぬようにそっと門を抜け、街の東方に向かった。
斉は、衛の東にある。距離は計りかねたが、心には明るい光があった。
――いま、私の本当の生が始まる。
そう自らに言い聞かせて、歩を進めた。
東門が近づいたとき、起はふと足を止めた。
門の前に、父・粛の姿があったのである。
(……読まれていたか)
内心にわずかな焦りが生じたが、いまさら退くわけにはいかぬ。すでに心は定まっていた。
父の前に立つと、起は一礼し、口早に別れの辞を述べた。
「父上、本日はお見送り、痛み入ります。私はこれより斉に赴き、学を修める所存にございます。どうかご自愛くださいませ。」
その声には、決意と怯えとがないまぜになっていた。
そして、急ぎ父の脇を通り抜け、門外へ出ようとした。
「待て、起よ。」
背後から、低く、くぐもった声が呼び止めた。
起は足を止め、深く息を吸った。
父の声が、自分を呼び止めたのだ。
思いもかけぬ温もりを含んだ声に、胸の内が揺れた。
しかし、なお足は動かず、しばしその場に立ち尽くした。
怯えとためらいが、心を塞いでいた。
(いま一歩でも後ずさげば、すべてを失う。)
己にそう言い聞かせ、震える心を押さえつけ、ゆっくりと身を返した。
振り返ると、父・粛は、涙をたたえた目で起を見つめ、穏やかに微笑んでいた。
起は息を呑んだ。父がこのような顔をするのを、見たことがなかった。
「起よ。もう、何も申すまい。行きたければ、行くがよい。」
そう言って、粛は小さな巾着を差し出した。
「旅費だ。ただし片道分のみぞ。」
父の声には、怒りも諫めもなかった。ただ、別れを受け容れる者の静けさがあった。
「馬鹿者が……達者でな。」
かすれた声に、父のすべての想いがこもっていた。
起はその場に立ち尽くし、涙を堪えきれなかった。
許された嬉しさ、背を押してくれた父への感謝、そして――帰還を許されぬ旅立ちであることを悟った哀しさ。
父・粛の微笑には、息子を信じ、送り出す親の情と、もはや二度と交わることのない道を選ばせた痛みとが、静かに滲んでいた。
起は深く頭を下げ、父の最期の優しさを胸に刻み、城門を出た。
公孫起、齢十七。
この日、衛の地を後にした。