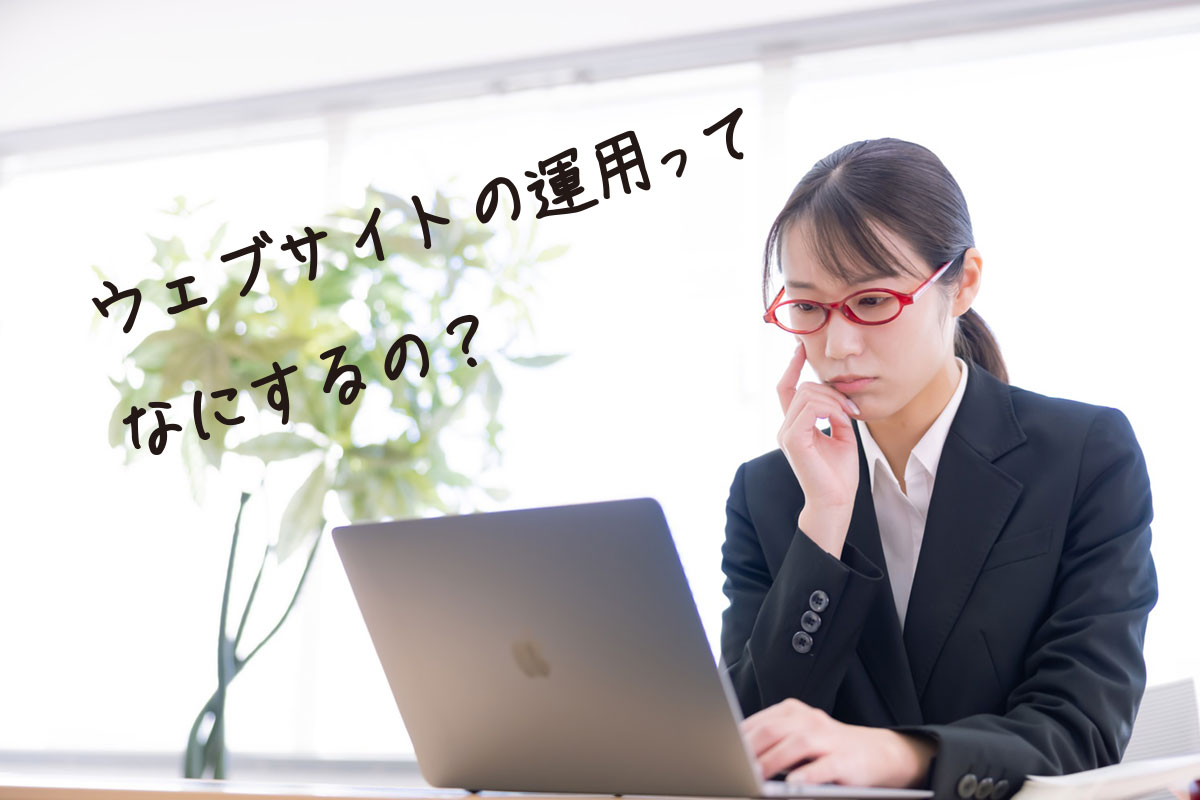僕の提供サービス・事業概要にある「WEBサイト運用・管理」でたまに質問をいただきます。
「管理」はWEBサイトの管理メンテナンスですね。質問をいただくのは「運用」の部分。
「運用」と聞くと、「資産運用」という言葉がありますが、「元手を使って資産を増やす」というイメージかと思います。
これと似ている?同じで、「WEBサイトを使って集客・ユーザー・来訪数を増やす」ということです。ユーザーや来訪数を増やすためには何をしなければいけないか、アクセス解析をしながら、ここはこうしたほうがいい、こういう情報発信をしたほうがいい、などをアドバイスして、実際にWEBサイトに手を加え、運用していきます。運営代行とも言えますかね。
WEBサイトを作りました、リニューアルしました、で何をするの?って方も多いでしょう。
今回はいわゆる「WEB担当者さん」向けに「WEBサイト運用」をおこなってきた経験から「WEBサイトで何をすればいいの?」的な話を記載したいと思います。
Contents
まずは基礎中の基礎「検索エンジン最適化(=SEO)」の設定確認を
業種や規模によっても色々ありますが、まずは共通部分で、新規作成された、リニューアルされたばかりのWEBサイトで「確認するべき」ことがあります。
それは、sitemap.xmlの存在とSearchConsoleと、タイトルタグなどの確認ですかね。場合に依っては「それはSEOで、別費用だ」という広告代理店さんとか制作会社さんもみえるかもしれませんが、基礎中の基礎すぎて、実施するのが当たり前のレベルですから、むしろ、「知らない」「用意していない」だった場合、そんな代理店さん、制作会社さんは危険です。
SEOの分野であり、それぞれを説明しだすと、それだけで1記事書けてしまうので、簡単にそれぞれ少しだけ説明記載します。
①sitemap.xmlの確認
sitemap.xmlの登録作業。sitemap.xmlとは、Googleなどの検索エンジンに「このWEBサイトにはこんなページがありますよー」と伝えるファイルで設置したほうが検索エンジン対策上有利です。
②SearchConsoleのアカウント取得
新規構築だった場合は、SearchConsoleを作る、もしくは共有してもらいましょう。SearchConsoleというのは、Googleが提供している「WEBサイトのカルテ」みたいなサービスで、sitemap.xmlもこのサービスを使ってGoogleに申請かけますし、下方に登場する「検索クエリ(=御社のサイトが検索結果に表示された際に検索されたワード)」を見ることが出来ます。
③タイトルタグの確認
各ページのタイトルタグはそのページを意味する内容になっているでしょうか?(WinならCtrl+U または、右クリックで「ページのソースを表示」で)
検索エンジンが検索されたワードに対して「選んでくる要素」といいましょうか。検索されたワードに対して、どんなサイトを引っ張ってくるか、という判断をする要素のなかでも最重要なのが
最近はGoogleが勝手に検索結果画面上で「こっちのほうがタイトルとして有益だ」ということでAIで判断してか、勝手に変えているときがあります。特にスマホですと短く省略されていたり、企業名しかない場合があります。
④メタディスクリプションの確認
何か検索した際にタイトルの下にある説明文的、概要的なものありますよね。あれがディスクリプションです。これは検索順位には影響しませんが、みなさんも検索した際に、ここの文書などを読んで「探している情報か?」というのを判断すると思います。そう、説明文を読んでページを開くか決める=つまりクリック率に影響します。これも各ページ、ディスクリプションは違うのが当たり前なのに、何故か全ページ同じにしてくる制作会社がいます(広告代理店がそういうことを知らずに制作会社に「テキトーに書いておいて」っていう場合もありますが)。
ただ、最近はGoogleが勝手に検索結果画面上で「こっちのほうがディスクリプションとして有益だ」ということでAIで判断してか、勝手に変えているときがあります。
⑤カノニカルタグの確認
「カノニカルタグ」というものがあります。確認出来る場所は上のタイトルタグを確認した場所と同じ、ソースコードを表示させて確認します。ソースコードを表示させて、Ctrl+Fでブラウザ内検索を表示させて
広告用のLPとかもですが、広告リンクやどのボタンからの流入を調べたりするときに「パラメーター」をつけたりすると思うのですが、パラメーターがつくと、別のURLと認識されたりします。ちょっと説明がややこしいので要約しますが、別のURLとなると、検索エンジンは「どっちが正しいの?」ってことになってしまうので、「正規URLはこれだよ」と伝えるタグになります。
カノニカルの注意事項として、「ちゃんと存在するURL」にすること。制作会社がカノニカルをよくわかっておらず、何も掲載されていない真っ白なテンプレートページを記述してしまい、検索結果に何も出てこないという作りになっていたことがあります。おそろしや。
⑥hタグの使い方の確認
「hタグ」(h1/h2/h3…といったタグ)がなにに当たっているか?「hタグ」はわかりやすい日本語でいうと、「見出し」です。大見出し、中見出し、小見出し・・・といった感じで各ページ内で使われます。
その見出しに使われているワードなどは「重要なワード」と検索エンジンに認識され、検索順位などに影響してきます。
最重要なh1タグを企業ロゴ画像に当てて、代替テキストで企業名入れている(=意味合い的にh1に会社名を当てている状態)のをよく見ます。色々な意見ありますが、個人的には非推奨です。だって、自社企業名の検索ってh1当てなくても基本的には引っかかります(新規公開の場合は公開当初は出てこないかもしれないですけど)。h1をロゴ画像にあてて自社名を最大強調ってのはちょっともったいないです。
自社サイトで「情報発信」を
自社サイトも「メディア」です。情報発信が出来るツールですから「自社媒体」です。「オウンドメディア」です。
WEBサイトに「お知らせ投稿」や「コラム」があるのであれば、「定期的な投稿」を心がけてください。たまに「当社のホームページを公開しました」とか「当社のホームページをリニューアルしました」しか記事がないWEBサイトがありますし、最新記事が数年前の状態で止まっているWEBサイトがあったりもします。これでは却って「お知らせ」機能や「コラム」がないほうがいい、という話になってしまいます。
どんな記事を投稿すればいいのか?
まずは「お客様(=御社事業の対象ユーザー)にとって役立つ情報である」でしょうか。これが最優先です。次いで「キャンペーン・イベント案内」などの告知でしょうか。別に会社の近隣のお店情報やグルメ情報でもいいんでしょうけど、御社のWEBサイトに来ているユーザーが「会社の近隣のお店情報やグルメ情報」が欲しくて来ているわけでもないでしょうし(※1)、更新担当者の「こんなとこに旅行行きました!」「こんなもの買ってきました!」的なものも求められていないと思います(※1)。
役立つ情報がない!思いつかない!
「役立つ情報」が特にない場合(色々と考えてみるとそれなりにネタはあるんですけどね)は、自社サイト内のページの紹介をしてみるのも手です。固定ページというか常駐ページというか。WEBサイト内にあるページが全てユーザーに閲覧されているとは限らず、そのWEBサイトの作りや、ユーザーのリテラシーや性格に依っては探している情報にたどり着いてないこともあります。そういったユーザー向けに、「お知らせ」として、「当社はこんなことやってますよ」「当社のサイト内にはこんな情報が掲載されています」なんてことを紹介するのも手のひとつです。階層が下のほうのページなどはなかなか見てもらえなかったりもありますからね。
ユーザーは思っているよりサイト内を見ていない
上記の事例でいうと、クライアント様のページで「公開してから半年間2桁台のアクセスだったページ」があったのですが、僕としては「このページはもっと需要あるよなぁ」と思い、(このときはメルマガとLINEでしたが※2)「こんなページありますよ、といった簡単な紹介で構わないので、『事例一覧』と、『費用について』のページを配信してみてください」と伝え、実施してみたところ、『費用について』は翌月のアクセスが4桁超えました。当然、そこから問い合わせも入りました(その後暫くは3桁後半維持していました)。興味のあるお客さんは勝手にサイト内を回遊して見てくれている、WEBサイトに置いておけば大丈夫というのは思い込みで、思っているよりユーザーは見ていません。アプリのプッシュ通知と同じで、見てほしい情報は前に出す、露出を高めるべきです。
※1:絶対にダメというわけではなく、これも高い精度や「突き抜け」て、この分野で集客が出来るようになれば、それはそれで武器になります。ただし、そこに集まったユーザーはその担当者の「ファン」になるかもしれませんが、企業にとってのユーザーや顧客になるかどうかは別の話です。
※2:SNSでも同じことが言えます。お知らせやコラムの機能がない場合はSNSでの情報発信が中心になると思いますが、「SNSで発信することがない」ではなく、事業の紹介や商品の紹介とか、サイト内のページにどんな情報が記載されているか、定期的な情報発信を心がけてください。SNSはもちろん、もっとくだけた内容でもいいので、「発信することがない」はあまりないことかとは思いますが、イベントやキャンペーンばかりの情報だとユーザーは飽きてしまうかもしれないので、たまに差し込むのもいいかもですね。
メンテナンス
メンテナンスと書くとシステムとかサーバーとか難しそうと思うかもしれないですが、それもメンテナンスですけど、そっちではなく、コンテンツ(=中身の記事やページ)のメンテナンスですね。
大きい企業さんですと、IR情報などを定期的に投稿されていたりしますが、例えば、企業情報や会社概要に「社員数」や「売上」を記載している場合は、その情報の書き換えが必要でしょう。また、法的に関わりがある部分(金融とか、不動産とか)で、法が変わったため、変更しないといけない場合は、併せて変更しないといけないです。これはコラムなども対象に入ります(それゆえ、◯◯年◯月◯時点の情報です、という記載で免責対処したりしています)。
あとは、成長性のあるコンテンツ・・・これはメンテナンスではないか・・・。
コンテンツの追加
コラム記事の追加とも似ていますが、成長性(=追加、シリーズ性)のあるコンテンツの追加ですね。例えば、制作事例や建築事例、導入事例などの「実績」の紹介。おそらく一番重要となるコンテンツになるんじゃないかな、と。ほかには、FAQなどのQ&Aも成長性のあるコンテンツです。「よくいただく質問」を記載しておくことで、検索で拾ってもらえることもあります。それだけでお客様の手間もスタッフさんの手間も省けます。あとはー、事例と似ていますけど、お客様の声とか。もちろん、これらの他にも、常に「どこか改善するべき場所はないか?」と注意深く隅々まで見ていく必要があります。ただ闇雲にサイト内を回遊しても分からないと思いますので、ここで重要となってくるのが「アクセス解析」です。
アクセス解析をおこないサイト内のページの数値を見て、「このページをもっと数字を伸ばしたい」とか「このページの滞在時間が短いからよく見てもらってないから対策を」とか、SearchConsoleから検索クエリを見て「表現や言葉をこう変えたほうがいいのでは?」とか、を検討しつつ、手を加えていきます。
Googleビジネスプロフィールなどの地図上の自社拠点
WEBサイトではないですが、もう無視出来ない存在になっているかと。仕様の差はあれど、Google/Yahoo/Bing/Appleなど各社似たようなサービス出していまして、クチコミや評価がついています。何か不祥事があると以前はWikipediaが荒れましたが、ここ最近はGBPが荒れることが多いです。自社拠点がGoogleMAP上にあって、まだオーナー申請されていない方は是非オーナー登録をしてください。また、必要ないと思っている方も念の為調べてください。第三者でも登録が出来ますし、勝手にGoogleが登録していることもあります。僕のクライアント様でも全く関係ないところに自社施設があったりしたこともありました。WEBサイトと同じく重要な媒体です。
GBPの詳細はこちら「Googleビジネスプロフィールあれこれ」や「2023年は地図サービスの開発競争が激化するかな?」でも紹介しています。
まとめ
よく「PDCAで回して改善を」という言葉はありますが、具体的になに?ってところもありますし、公開直後とかリニューアル直後で改善というのも、思いつかないですよね。リニューアルや新規構築前にWEBサイトが出来たらあれやろう、これやろうが決まっていて、計画や人員が充実していればそれらを実行すればいいのですが、そういったものが決まってなかった場合、「作って終わり」になってしまいます。
WEBサイトは成長させるものであり、作って終わりではなく、作ってからがスタートです。商品やサービスを充実させてページをブラッシュアップして、コラムなどがあるなら有用な記事で見込み客やファンを増やし、事例や利用者、オーナーの声で自社の評判を高める。業種や規模によっても違いますが、時折WEB広告なんかも交えたり、あとは無視出来ないSNSなどで見つけてもらいやすくしたり、ユーザーと交流を図ったりして、アクセス解析をおこない、結果を見て問題点を見つけ改善させていく。そんなところでしょうか。